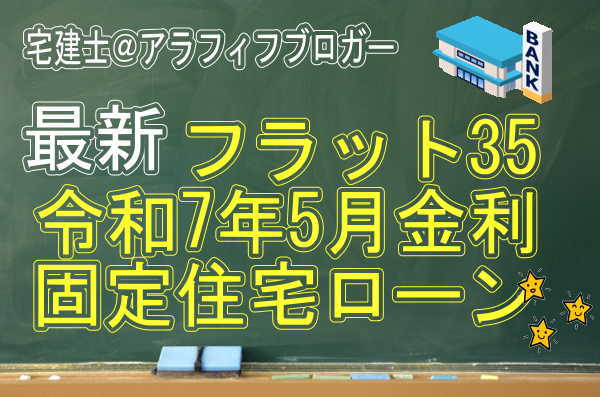令和7年度:宅地建物取引士試験対策

後輩が1年1回しかない
令和7年に宅建試験に挑戦
話が広がり弊社だけではなく
付き合いのある不動産会社の社員を
含めて合同で私が勉強会を開催
指導方法はオリジナル
若手の合格率に直結するので
全力を尽くします
それなら
折角・私が勉強会で実施した方法
皆にも参考になればと掲載して
行こうと思います
過去問3年間分をサーキット方式

宅建試験概要:受験資格・費用等
前回記事で見れますココから要確認
☆実際に使った書籍シリーズを
貼り付けておきますので
見てみてください
個人的な考えですが過去問は
5年前まで遡れば十分
理由は古すぎるのは近年での
変更点と差異が大きいから
その為、令和7年度試験では
令和2年まで過去問を隙間時間で
サーキット方式でやり続けますが
仕事が忙しい人は3年前までの
令和4年までで良いです
それをひたすら
やり続けてみてください
そして間違った箇所と
正解だったけど判らず
1/4の確率で選んで偶然正解した
箇所も含めて、ここで参考書に戻る
これのみです
さあ悩むより行動です
早速、令和6年度・過去問
第3問目を始めましょう
下に説明を加えて記載
挑戦してみてください
令和6年度:宅建試験過去問・第3問

宅建試験:令和6年 過去問です
間違っても良いのでやりましょう
【問 3】 甲土地につき
A・B・C・Dの4人が
それぞれ4分の1の共有持分を
有していてA・B・Cのいずれも
Dの所在を知ることが
できない場合に関する
次の記述のうち、民法の規定
及び判例によれば
正しいものはどれか
なおDの共有持分は
相続財産には属して
いないものとする
1番:甲土地にその形状又は
効用の著しい変更を
伴う変更を加える場合には
共有者の過半数の同意が
必要であり本件では
A・B・C3人の同意が必要となる
2番:甲土地の所有権の
登記名義人となっている者が
所有者ではないEである場合
持分に基づいてEに対して
登記の抹消を求めるためには
所在が判明している
A・B・Cのうち2人の
同意が必要である
3番:A・B・C3人の
同意があれば甲土地を
資材置場として賃借したい
Fとの間で期間を3年とする
賃貸借契約を締結することができる
4番:Aが裁判所に請求して
裁判所がDの持分をAに取得させる
旨の決定をした場合Dは
その決定から3年以内に限り
Aが取得したDの共有持分の
時価相当額をAに対して支払う
よう請求することができる
答えは次のブロックに記載
第3問の答え:令和6年度:宅建試験過去問

第3問の答え:令和6年度:宅建試験過去問
正解は3番
以下にその理由は
【選択肢1】
甲土地にその形状又は
効用の著しい変更を
伴う変更を加える場合には
共有者の過半数の同意が
必要であり本件では
A・B・C3人の同意が必要となる
2番:甲土地の所有権の
登記名義人となっている者が
所有者ではないEである場合
持分に基づいてEに対して
登記の抹消を求めるためには
所在が判明している
民法の規定・民法第251条
各共有者は他の共有者の同意を
得なければ共有物に
変更を加えることができない
ここでいう変更とは単なる使用
収益を超える物理的な改変
または性質の変更等共有物に対し
性質上の重大な影響を及ぼす
行為を指します
つまり形状や効用の著しい変更は
共有者全員の同意が必要となる
解釈
共有者の過半数の
同意でよいという記述は誤り
著しい変更には
全員の同意(全員一致)が必要
Dが所在不明であっても
失踪宣告などがなされて
いない限り持分権は存続
同意権も保持しています
結論:選択肢1は誤り
【選択肢2】
甲土地の所有権の
登記名義人となっている者が
所有者ではないEである場合
持分に基づいてEに対して
登記の抹消を求めるためには
所在が判明している
A・B・Cのうち2人の
同意が必要である
民法及び登記実務視点
共有物について不実の登記
真実でない登記が存在し
それを抹消したい場合
一般にその持分に関する
登記の抹消を請求する権利は
各共有者が自らの持分について
個別に有するとされています
例としてDの持分が誤って
Eに登記されていたとしても
他の共有者A・B・Cは
自己の持分に基づいて
単独で自己の権利に影響する
部分の抹消を請求できます
抹消請求には他の共有者の
同意は不要である為
自らの持分についての
権利行使をするのに
他人の同意は要らないとなる
結論:選択肢2は誤り
【選択肢3】
A・B・C3人の
同意があれば甲土地を
資材置場として賃借したい
Fとの間で期間を3年とする
賃貸借契約を締結することができる
(正解肢)
A・B・C3人の同意があれば
甲土地を資材置場として
賃借したいFとの間で期間を
3年とする賃貸借契約締結可能
民法第252条
共有物の管理に関する事項は
各共有者の持分の価格に従い
その過半数で決する
管理に関する事項とは
共有物の通常の使用
維持・保存・収益
賃貸借契約など物理的な
改変を伴わない
一般的な利用を指します
補足説明
賃貸借契約は管理行為
甲土地を資材置場として
貸すことは典型的な管理行為に該当
A・B・Cの3人で持分の
3/4(=75%) を有しており
過半数(1/2超)に該当
Dの所在が不明であっても
持分は依然として1/4であり
意見を表明できないが
過半数が得られていれば
管理行為は可能
結論:選択肢3は正しい
(正解肢)
【選択肢4】
Aが裁判所に請求して
裁判所がDの持分をAに取得させる
旨の決定をした場合Dは
その決定から3年以内に限り
Aが取得したDの共有持分の
時価相当額をAに対して支払う
よう請求することができる
Aが裁判所に請求して
裁判所がDの持分を
Aに取得させる旨の決定をした場合
Dはその決定から3年以内に限り
Aが取得したDの共有持分の
時価相当額をAに対して
支払うよう請求することができる
民法第262条の2
(共有物分割に関する判決)
これは主に所在不明共有者に関する
持分取得の制度(不在者の持分取得)に
関わる内容を意識したものと
考えられ・実際の制度としては
共有物分割請求訴訟等の
文脈でしか共有持分の取得が
強制されることはなく
特別な取得制度は存在しません
加えAがDの持分を裁判所の
決定によって取得するような
法的制度は現行民法にはなく
仮に失踪宣告を経て相続が
生じた場合であっても一定の
法定手続を経なければならない
ちなみに3年以内の請求という
規定も民法には存在しません
結論:選択肢4は誤り
以下で詳しく説明を書きます

最終結論:正解は【3】
補足説明として
関連知識深掘り
(共有と所在不明者)
所在不明共有者と管理行為
民法第252条の解釈において
共有者のうちの1人が所在不明で
あっても過半数が確保されて
いれば管理行為は可能とされ
これにより全会一致を要する
変更・処分行為とは明確に区別されます
変更・処分行為との違い
管理行為:過半数の同意
(民法252条)
例として:通常の賃貸借契約・修繕・収益活動
変更行為:全員一致(民法251条)
例として:建物の取り壊し
大規模造成工事
処分行為:共有物そのものの売却など
実質的には全員一致または
持分売却手続きの活用が必要
まとめとして
選択肢 内容概要 結論 理由
1番:形状・効用の著しい変更は
過半数の同意・ 変更行為には
全員一致が必要(民法251条)
2番:不実登記の抹消には2人の
同意が必要 ・ 持分権者は単独で
自らの権利を行使できる
3番:資材置場として3年賃貸するには
ABCの同意で足りる管理行為であり
持分の過半数で足りる(民法252条)
4番:AがDの持分を取得
Dが3年以内に時価相当額の請求可能
そのような制度・規定は存在しない

宅地建物取引士試験に近道なし

国家試験対策で
難しい事はしません
シンプルイズベストです
私は宅地建物取引士の専門学校に
通わず独学で約3ヶ月(約96日)
勉強し1回目のテストで合格
教材もインターネットで販売している
数千円の書籍を数冊買っただけ
(教材総費用:9600円くらい)
注:5問免除は使わなかったので
普通の50問試験を受験
問題集と参考書のみで
サーキット方式で進めます
個人的なやり方なのですが
最初は参考書は読みません
問題集を先にやります
此処で間違っても大丈夫♪
間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
箇所も含めて、後で参考書で調べます
名付けて
逆打ち勉強法です
悩むより量稽古・隙間時間があったら
ひたすら過去問をやり
ひたすら間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
箇所も含めて、後で参考書で調べます
この時に参考書を読んでも理解できない
事が出てきますので社内講師の出番
実際に若手にした内容を
1問・1答で説明を記載しました
参考にしてください
次回記事の予告

宅建士じつ
アラフィフ不動産ブログ
最後まで読んで頂き
ありがとうございます
次回は令和6年度
試験問題:4番を
触れてみたいと思います
是非、登録して読み続けてくださいね
よろしくお願いいたします
「see you again」
☆関連する記事
国家資格の宅建士って?
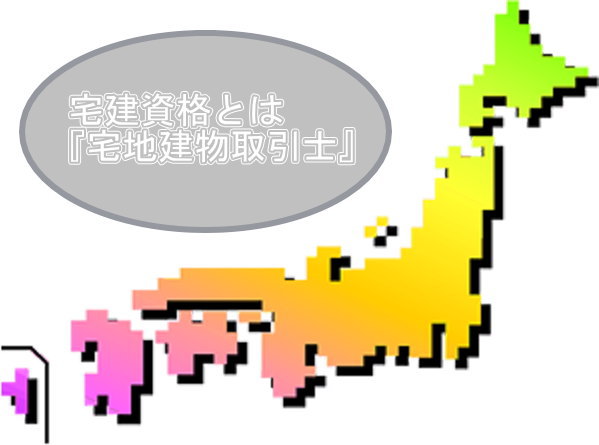

株式投資も副収入で視野に入れる
☆住宅を検討予定の人にお勧め記事
住宅ローン・フラット35:2025年5月固定金利情報