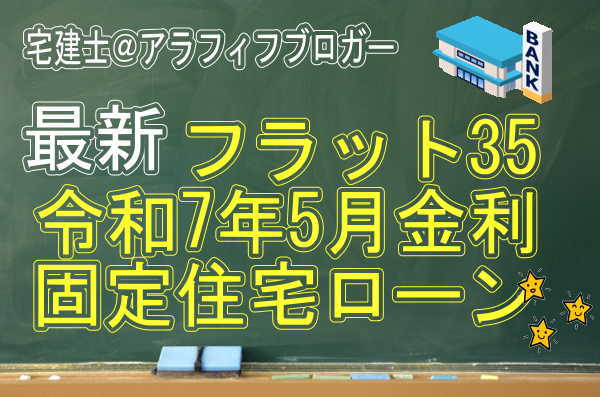令和7年度:宅地建物取引士試験対策

前回に書き込みした
後輩が1年1回ある
(秋に開催)
令和7年に宅建試験に挑戦
話が広がり弊社だけではなく
付き合いのある不動産会社の社員を
含めて合同で私が勉強会を開催
指導方法はオリジナル
若手の合格率に直結するので
全力を尽くします
ここで
折角なら私が勉強会で実施した方法
皆にも参考になればと掲載して
行こうと思います
過去問3年間分をサーキット方式

宅建試験概要:受験資格・費用等
前回記事で見れますココから要確認
☆実際に使った書籍シリーズを
貼り付けておきますので
見てみてください
私の考えですが過去問は
5年前まで遡れば十分です
理由は古すぎるのは近年での
変更点と差異が大きい為です
その為、令和7年度試験では
令和2年まで過去問を隙間時間で
サーキット方式でやり続けますが
仕事が忙しい人は3年前までの
令和4年までで良いです
それをひたすら
やり続けてみてください
そして間違った箇所と
正解だったけど判らず
1/4の確率で選んで偶然正解した
箇所も含めて、ここで参考書に戻る
これのみです
さあ悩むより行動です
早速、令和6年度・過去問
第2問目を始めましょう
令和6年度:宅建試験過去問・第2問

宅建試験:令和6年 過去問です
間違っても良いのでやりましょう
【問 2】
委任契約・準委任契約に関する
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、
誤っているものはどれか
1 売主が、売買契約の付随義務として、買主に対して、マンション専有部分内の防火戸の操
作方法につき説明義務を負う場合、業務において密接な関係にある売主から委託を受け、売
主と一体となって当該マンションの販売に関する一切の事務を行っていた宅地建物取引業者
も、買主に対して、防火戸の操作方法について説明する信義則上の義務を負うことがある。
2 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受
任者を選任することができない。
3 委任契約で本人が死亡しても代理権が消滅しない旨を合意して代理人に代理権を与えた場
合、本人が死亡しても代理権は消滅しない。
4 委任は、当事者の一方が仕事を完成することを相手方に約し、相手方がその仕事の結果に
対しその報酬を支払うことを約さなければ、その効力を生じない。
答えは次のブロックに記載
第2問の答え:令和6年度:宅建試験過去問

第2問の答え:令和6年度:宅建試験過去問
正解は4番
以下にその理由は
【選択肢1】
売主が売買契約の付随義務として
買主に対してマンション専有部分内の
防火戸の操作方法につき説明義務を
負う場合・業務において密接な関係に
ある売主から委託を受け売主と一体と
なって当該マンションの販売に関する
一切の事務を行っていた
宅地建物取引業者も買主に対して
防火戸の操作方法について
説明する信義則上の義務を負うことがある
1番は:正しい
記述は判例
(最判平成19年3月27日)に
基づく正しい記述
この判例はマンション販売で
売主と密接な関係にあり
売主が一体的に販売活動を行っていた
宅地建物取引業者について
買主に対して信義則上の
情報提供義務を負うことが
あると判断された例です
防火戸の操作方法など
安全性や重要事項に関わる
説明がなされていない場合は
黙示的説明義務違反が
問われる可能性がありえます
【選択肢2】
受任者は委任者の許諾を得たとき
又はやむを得ない事由が
あるときでなければ復受任者を
選任することができない
2番は:正しい。
民法第1056条(旧644条)
に規定されている内容
復代理人(復受任者)は
原則として本人(委任者)の
許可が必要
やむを得ない事由
(例えば病気など)により
本人許諾が得られない場合
例外的に復代理人を選任する
ことが可能であり
この条文の趣旨は
復代理人の選任によって
本人に損害が及ぶ
リスクを防ぐ点にあります
【選択肢3】
委任契約で本人が死亡しても
代理権が消滅しない旨を
合意して代理人に代理権を
与えた場合本人が死亡しても
代理権は消滅しない
3番は:正しい
民法第111条ただし書
(代理に関する規定)に
基づく判例法理に則った記述
代理権は本人の死亡に
よって消滅します
(民法第111条)
本人が死亡しても代理権を
消滅させない旨の合意が
当事者間にある場合は
特約により代理権は存続する
というのが判例及び学説です
特に遺言執行などの文脈で
この合意が活用する時もある
【選択肢4】
委任は当事者の一方が仕事を
完成することを相手方に約し
相手方がその仕事の結果に対し
その報酬を支払うことを
約さなければその効力を生じない
4番は:誤り(正解肢)
この記述は請負契約の要件に
関する内容で委任契約の
説明としては誤っています
以下で詳しく説明を書きます

【委任契約・準委任契約の性質】
民法において委任契約や
準委任契約は仕事の完成を
目的とするものではなく
一定の法律行為または事務を
善良な管理者の注意をもって
遂行することを内容とする契約
補足説明として
【委任契約】
民法第643条(委任)
委任は当事者の一方が、
法律行為をすることを
他の一方に委託し
相手方がこれを承諾することに
よってその効力を生ずる
この条文が示すように
委任契約の目的は仕事の完成ではなく
法律行為の遂行です
例として代理人が契約を締結する
訴訟代理を行うなどの行為が該当します
【準委任契約】
委任契約の法律行為に対し
準委任契約は法律行為以外の
事務処理を目的とします
例として医師が診察を行う行為
弁護士が助言を与える行為
コンサルタント業務などがある
【請負契約との違い】
選択肢4の記述は
次の条文の内容を述べている
民法第632条(請負)
請負は当事者の一方がある
仕事を完成することを約し
相手方がその仕事の完成に対し
報酬を支払うことを
約することによって効力を生ずる
すなわち仕事の完成が目的である
契約は請負契約であり
委任契約は仕事の遂行
(完成ではない)が目的
これが両者の決定的違いになる
【報酬の有無と契約の効力】
もう少し補足すると委任契約は
報酬有無にかかわらず効力が生じ
民法第648条は
以下のように定めています。
民法第648条第1項
委任が有償であるか無償であるかは
その契約または当事者の意思によって定まる
報酬の約束がなければ契約が
無効になるということはなく
報酬がなくても有効な
契約が成立します
この点でも選択肢4は
委任契約に当てはまりません。
【結論】
選択肢4は請負契約に関する説明で
委任契約・準委任契約の要件に
該当しないため
誤りであるといえます
民法の規定および委任
準委任契約の性質を正しく
理解できれば
この選択肢が明らかに
誤りであることが分かります

宅地建物取引士試験に近道なし

難しい事はしません
シンプルイズベストです
私は宅地建物取引士の専門学校に
通わず独学で約3ヶ月(約96日)
勉強し1回目で合格しました
教材もインターネットで販売している
数千円の書籍を数冊買っただけ
(教材総費用:9600円くらい)
注:5問免除は使わなかったので
普通の50問試験を受けました
問題集と参考書のみで
サーキット方式で進めます
個人的なやり方なのですが
最初は参考書は読みません
問題集を先にやります
此処で間違っても大丈夫♪
間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
箇所も含めて、後で参考書で調べます
名付けて
逆打ち勉強法です
悩むより量稽古・隙間時間があったら
ひたすら過去問をやり
ひたすら間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
箇所も含めて、後で参考書で調べます
この時に参考書を読んでも理解できない
事が出てきますので社内講師の出番
実際に若手にした内容を
1問・1答で説明を記載しました
参考にしてください
次回記事の予告

宅建士じつ
アラフィフ不動産ブログ
最後まで読んで頂き
ありがとうございます
次回は令和6年度
試験問題:3番を
触れてみたいと思います
是非、登録して読み続けてくださいね
よろしくお願いいたします
「see you again」
☆関連する記事
国家資格の宅建士って?
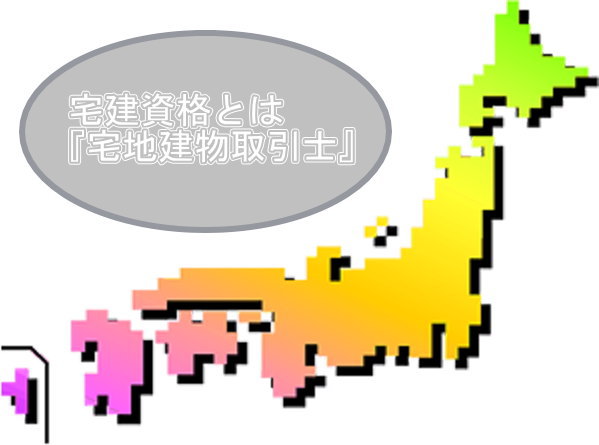

株式投資も副収入で視野に入れる
☆住宅を検討予定の人にお勧め記事
住宅ローン・フラット35:2025年5月固定金利情報