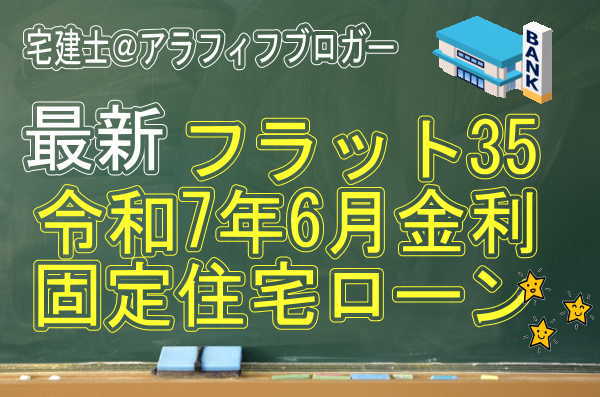2025年度:宅建テスト対策

2025年の秋
本業で勤務している
不動産会社の若手達が
宅建試験に挑みます
合格率が低い近年に対応で
私が社内講師に任命され
独自の勉強会を開く事になった
その話が廻りに広がり
付き合いがある不動産会社の
スタッフも参加する事になり
各社より指導方法は私の
オリジナルで許可を頂いたが
受験者の合格率に直結するので
私も全力を尽くします
折角・私が勉強会で実施した方法
皆にも参考になればと掲載して
行こうと思います
過去問3年間分を繰り返しやる

宅建試験概要:受験資格・費用等
前回記事で見れますココから要確認
☆私が実際に宅建勉強で使った
書籍シリーズを掲載していますので
参考にしてください
私の個人的な考えですが
宅建試験対策は参考書を読まず
一番初めに過去問を5年前まで
遡り始めるのが大事
10年前の出題は近年での
変更点と差異が大きい為・不要
令和7年度試験では
令和2年まで過去問をグルグル
サーキット方式でやりましょう
新入社員は雑務も忙しいので
3年前までの問題
令和4年迄で良いです
今の時期は過去問を
やり続けてください
そして間違った箇所と
偶然・正解だったが
なんとなく選んで正解した
箇所も含めて、ここで参考書を見る
これのみです
悩むより行動する時です
過去問を(令和6年度)
さあ第12問目を始めましょう
下に説明を加えて問題を記載
挑戦してみてください
令和6年度:宅建試験過去問・第12問

宅建試験対策で最重要は
令和6年 過去問です
6月下旬・今は時間をつくり
間違っても良いのでやります
【問 12】
賃貸人Aと賃借人Bとが
居住目的で期間を3年として
借地借家法第38条の
定期建物賃貸借契約
(以下この問において「契約①」という。)
を締結した場合と、定期建物
賃貸借契約でも一時使用目的の
賃貸借契約でもない
普通建物賃貸借契約
(以下この問において「契約②」という。)
を締結した場合とに関する
次の記述のうち、
借地借家法の規定によれば、
正しいものはどれか
1番:Bが建物の引渡しを受けた後に
Aが建物をCに売却して
建物所有者がCに変わった場合、
Bは契約①の場合ではCに対して
賃借人であることを主張できるが
契約②の場合ではCに対して
賃借人であることを主張できない
2番:契約期間中は賃料の改定を
行わない旨の特約を契約において
定めていても、契約期間中に賃料が
不相当になったと考えるに至ったBは
契約①の場合も契約②の場合も
借地借家法第32条に基づく
賃料減額請求をすることができる
3番:Bが契約期間中に相続人なしで
死亡した場合において
婚姻はしていないが事実上夫婦と
同様の関係にあった同居者Dが
あるときは契約①の場合も
契約②の場合もAに反対の意思表示を
しないDは建物の賃貸借契約に
関しBの権利義務を承継する
4番:契約①の場合
公正証書によって契約をするときに
限り契約の更新がないことを有効に
定めることができ
契約②の場合、書面で契約し
かつAに正当な理由がない限り
Aは契約の更新を拒絶することができなくなる
答えは次のブロックに記載
第12問の答え:令和6年度:宅建試験過去問

第12問の答え:
令和6年度宅建試験過去問
正解は3番
問題文の構造と前提整理
この問題は借地借家法に基づく
2つの契約形態についての違いと
それに伴う法律効果を聞いています
【契約①】
定期建物賃貸借契約
(借地借家法38条)
居住目的:契約期間:3年
契約更新がない特約がある
(基本的に更新なし)
契約締結には書面が必須
公正証書である必要はないが
説明義務あり
【契約②】
普通建物賃貸借契約
(借地借家法の一般原則)
更新あり(合意・法定更新)
正当事由がなければ
貸主からの解約は困難
通常居住用物件に
おける一般的な契約形態
———————–
◆ 条文に基づく正確な根拠
借地借家法 第36条
(賃借人の死亡等)
建物の賃借人が死亡した場合に
その者と同居していた親族その他
これに準ずる事情にある者で
婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情に
あるものがあるときは
当該者が反対の意思を表示しない限り
建物の賃貸借契約に基づく
賃借人の権利義務を承継する
◆ 解釈と趣旨
借家契約は生活基盤を
守ることが目的です
特に事実婚(内縁)のように
法律上の婚姻ではないが
実質的に家族同然の関係に
ある者に対しても住宅の
継続的使用を保障する必要がある
この為・親族に限定せず
これに準ずる事情にある者にも
保護を広げています
◆ ポイント整理
要素 内容
対象 同居していた内縁の配偶者など
要件 ①同居していたこと
②事実上の婚姻関係
(社会通念上の夫婦)
効果 賃借人としての地位
義務を引き継ぐ(当然承継)
反対意思表示 特段の反対の
意思がなければ自動的に承継される
◆ 具体例
事例1:賃借人B(男性)賃貸人A
Bは、事実婚状態の女性Dと
10年間同居・生活費共有
近所からも夫婦と認識されていた
Bが死亡した後・DがAに
この家に住み続けたいと申し出た
AはDの承継を拒否できない
Dは賃借人としての権利を承継できる
設問の選択肢ごとの詳細な解説
1番:売却後の賃借人の地位の対抗可否
【誤り】契約①では主張できるが
契約②ではできないとあるが
逆または両方とも主張できる
【理由】
どちらの契約形態でも建物の
引渡しを受けた後であれば
対抗可能(借地借家法31条)
【参考条文】
借地借家法 第31条
賃借人が建物の引渡しを
受けた場合にはその賃貸借は
第三者に対してその効力を生ずる
【補足説明】
所有権がCに移っても賃借人が
引渡し済みであれば
新所有者にも対抗できる
契約①・②どちらでも同じ効果がある
1番は誤り

2番:賃料減額請求
(借地借家法32条)
【誤り】契約①でも賃料減額
請求ができるとしている
【理由】
契約①(定期建物賃貸借契約)は
賃料改定請求の対象外にする
特約が可能
【参考条文】
借地借家法 第38条第6項
賃料の額について別段の
定めがあるときはその定めに従う
この文言により契約①では
賃料改定請求権を排除できる
一方で契約②では排除できない為
賃料改定は原則認められる
2番は誤り

1番:所有者変更後の対抗力の有無・誤り
2番:賃料改定請求の可否・誤り
3番:同居の事実婚者による承継・正しい
4番:定期契約の更新拒絶要件・誤り
3番は正解
借地借家法 第36条
(賃借人の死亡等)
建物の賃借人が死亡した場合に
その者と同居していた
親族その他これに準ずる事情に
ある者で婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情に
あるものがあるときは
当該者が反対の意思を表示しない限り
建物の賃貸借契約に基づく
賃借人の権利義務を承継する
◆ 解釈と趣旨
借家契約は生活基盤を
守ることが目的です
特に事実婚(内縁)のように
法律上の婚姻ではないが実質的に
家族同然の関係にある者に対しても
住宅の継続的使用を
保障する必要があります。
このため親族に限定せず
これに準ずる事情にある者に
まで保護を広げています
4番:更新拒絶条件
【誤り】契約①は公正証書で
なければ更新拒絶できないと
あるが誤りです
【契約①】
書面による契約が必要で
公正証書である必要はない
更新拒絶の特約も
書面で明示すれば有効
【契約②】
正当事由がなければ
貸主から更新拒絶不可
(借地借家法26条)
【参考条文】
借地借家法 第38条第2項
定期建物賃貸借契約は
書面により契約しなければならない
公正証書である必要はない
(書面要件のみ)
4番は誤り
補足説明として
実務における適用判例
◆ 判例1(東京地裁平成25年)
事実婚のパートナーが反対意思を
示さなかった為
死亡した賃借人の地位を当然に承継
(借主の生活安定を重視)
◆ 実務上の注意点
項目 実務でのポイント
内縁関係の証明・同居期間
生活実態・周囲の証言
扶養実績など
定期契約説明義務・書面の交付
更新なしの説明義務
(説明不足だと普通契約にみなされる)
賃料改定条項 「改定不可」と
書いても普通契約では
公序良俗違反で無効となることも
まとめと学習ポイント
契約① 定期建物賃貸借契約
更新なし・書面必須・賃料特約有効
契約② 普通契約・更新あり
正当事由が必要
事実婚の同居者・条件を満たせば
当然に契約を承継
(反対意思がなければ)
所有者変更・両契約とも
建物引渡し後であれば
新所有者に対抗できる
賃料改定・契約②は
常に請求可能
契約①は特約により排除可能
私からのアドバイス
「契約①は特約が強く、契約②は借主が強い」

この理解を基に選択肢を
検討すれば正解は3番である
まだ時間はあります
頑張りましょう・応援します
宅地建物取引士試験に近道はない

宅建勉強を含め国家試験対策で
難しい事をする必要はなく
シンプル・イズ・ベスト
私は宅地建物取引士の専門学校に
通わず独学で約3ヶ月(約96日)
過去問をサーキット方式で
隙間時間をみつけて勉強し
1回目の受験でテスト合格
教材もインターネットで
普通に販売している本のみ
千円代の書籍を数冊買っただけ
(教材総費用:9600円くらい)
注:5問免除は使わなかったので
普通の50問試験を受験
問題集と参考書のみで
繰り返しやりなおして
進めるだけ
ポイント:
私の個人的なやり方ですが
最初は参考書は読みません
問題集を先にやります
此処で間違っても全然OK♪
間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
箇所も含めて、参考書で調べます
名付けて
逆打ち勉強法と言います
悩むより量稽古・隙間時間があったら
ひたすら過去問をやり
ひたすら間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
問題も上記と同じで参考書で調べます
参考書を読んでも理解できない事が
出てきますので社内講師が必要
実際に若手にした勉強法・説明を
1問・1答で説明を記載しました
参考にしてください
合格イメージが大事
モチベーション維持にも
祝賀会を目指して
頑張ってみてください
応援しています
次回記事の予告

宅建士@じつ
アラフィフ不動産ブログ
最後まで読んで頂き
ありがとうございます
次回は令和6年度
試験問題:13番に
触れてみたいと思います
是非、登録して読み続けてくださいね
皆の合格を願っています
よろしくお願いいたします
「see you again」
☆関連する記事
国家資格の宅建士って?
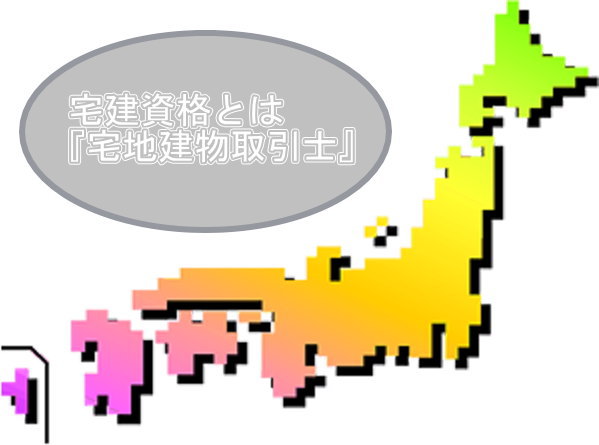

株式投資も副収入で視野に入れる
☆住宅を検討予定の人にお勧め記事
住宅ローン・フラット35:2025年6月固定金利情報